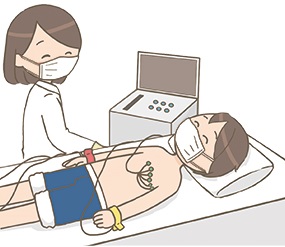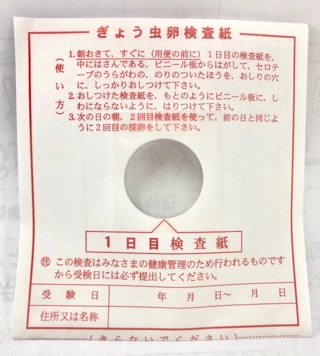学校検尿では、尿中に、蛋白、赤血球、糖、ウロビリノーゲンがでているかどうかの検査が行なわれています。腎盂腎炎は初期には無症状で経過し、放置されると将来腎不全に移行することが知られており、学校検尿で早期に発見されることが多くあります。また生活習慣の変化に伴う若年者2型糖尿病の発症も報告され、糖尿検査により糖尿病の早期発見にもつながります。これらの病気を早期発見・早期治療することで将来の疾病の重症化を予防するために検査します採尿の注意点 正しい検査結果を得るために…①
前日の夕食は、暴飲暴食を避けて下さい。 ② 就寝前には、ジュース類やビタミンC剤などを過剰に摂取しないで下さい。 ③ 夜遅くまで激しい運動を行うなど、前夜は疲労しないようにして下さい。④女子で生理中の人は、提出しないで下さい。生理前3~4日、生理後5~6日は尿潜血反応の信憑性が著しく低下するとされているため、生理の前後数日間は避けましょう⑤精液が混ざるとタンパク質による影響が出ることがあります。
検査の前日は、性行為・自慰行為も控えるようにしましょう。

弊社では、2024年4月検査分より、下記の尿自動分析装置、及び学童検診システムを導入することとなり、それに伴い採尿容器の変更、及び採尿頂いた検体へのバーコード貼付をお願いすることとなりました。
各御施設様につきましては、これまでの運用とは少し違ったやり方をお願いする事になりますが、宜しくお願いいたします。
検診システム導入後は、尿検査結果や検査統計表の迅速報告、検査漏れ生徒(園児)様の早期把握、検査陽性者の早期医療期間受診のなど、メリットが多く、弊社といたしましてもより正確な検査、医療事故防止の観点から双方にとって、有用な変更となりますので、何卒ご理解頂きますようお願いいたします。